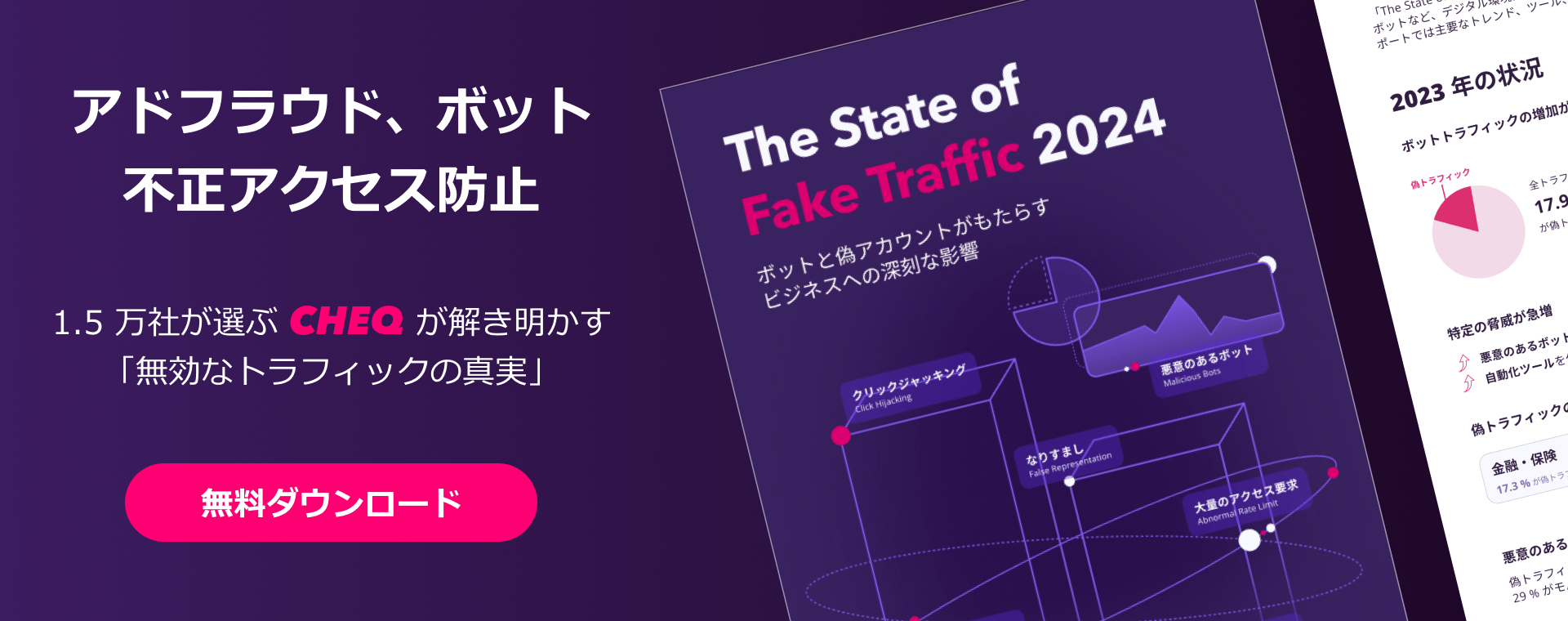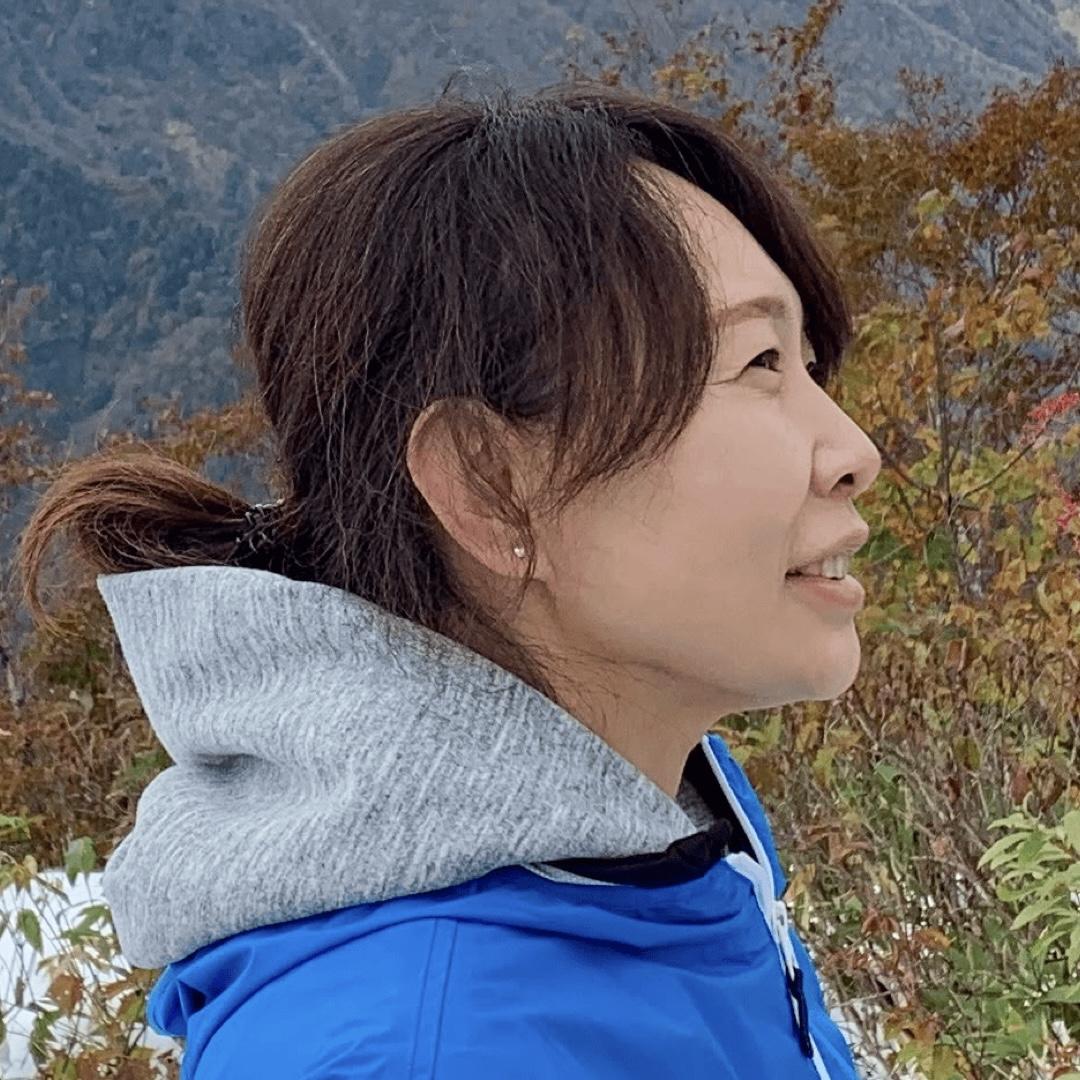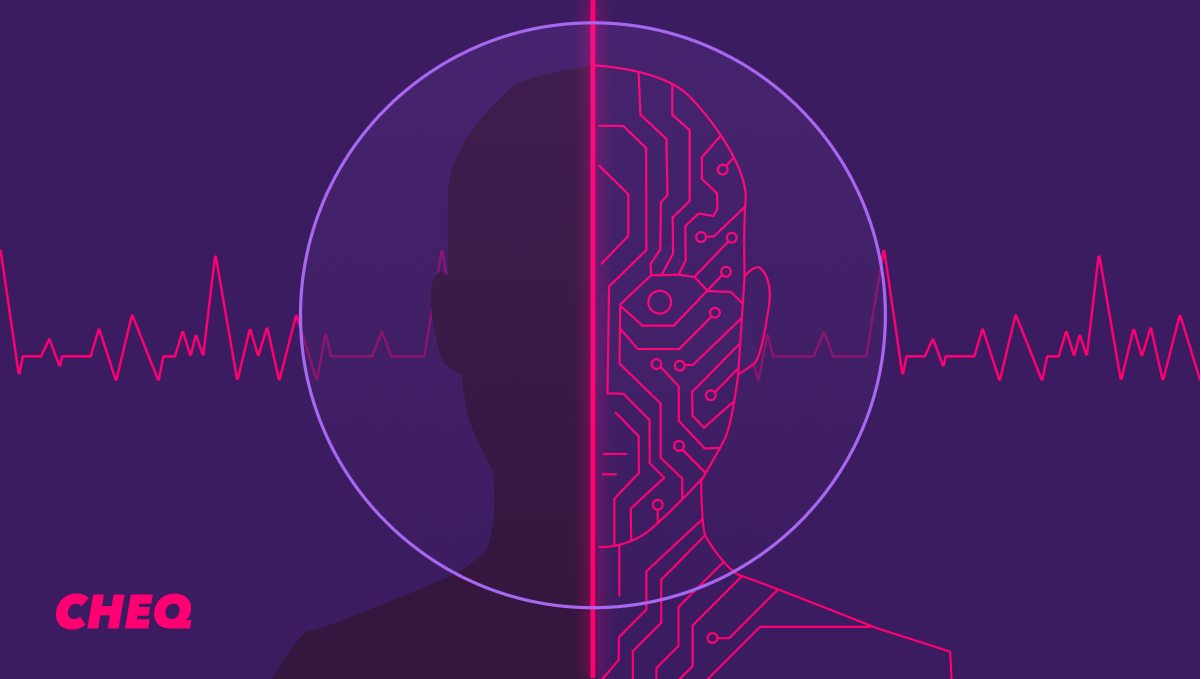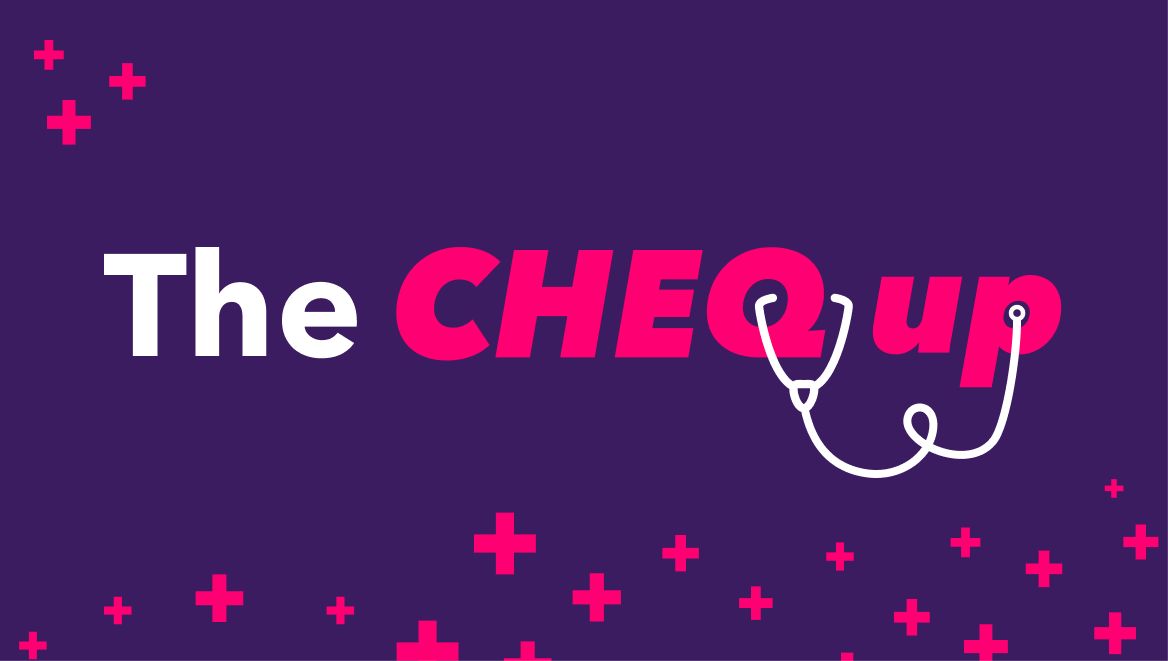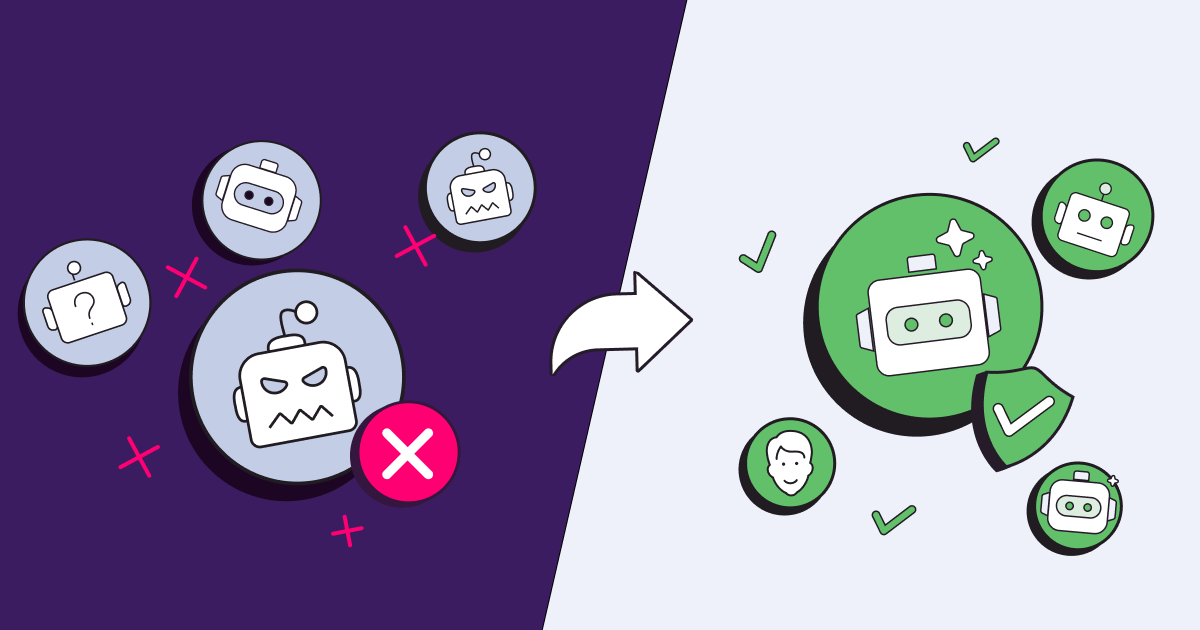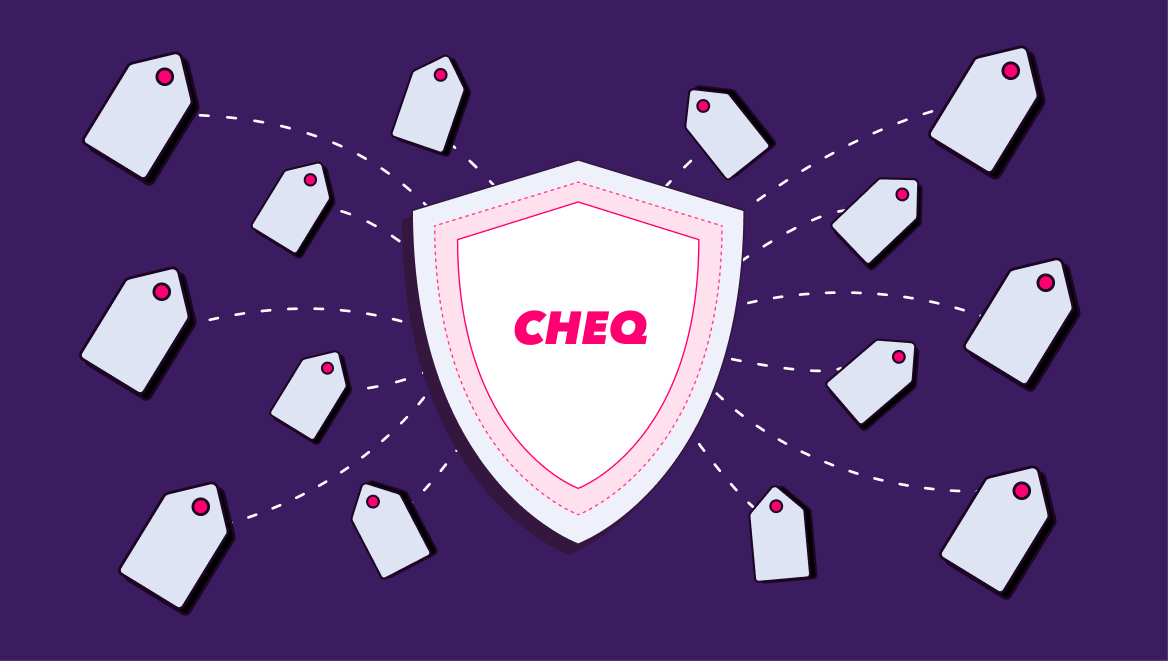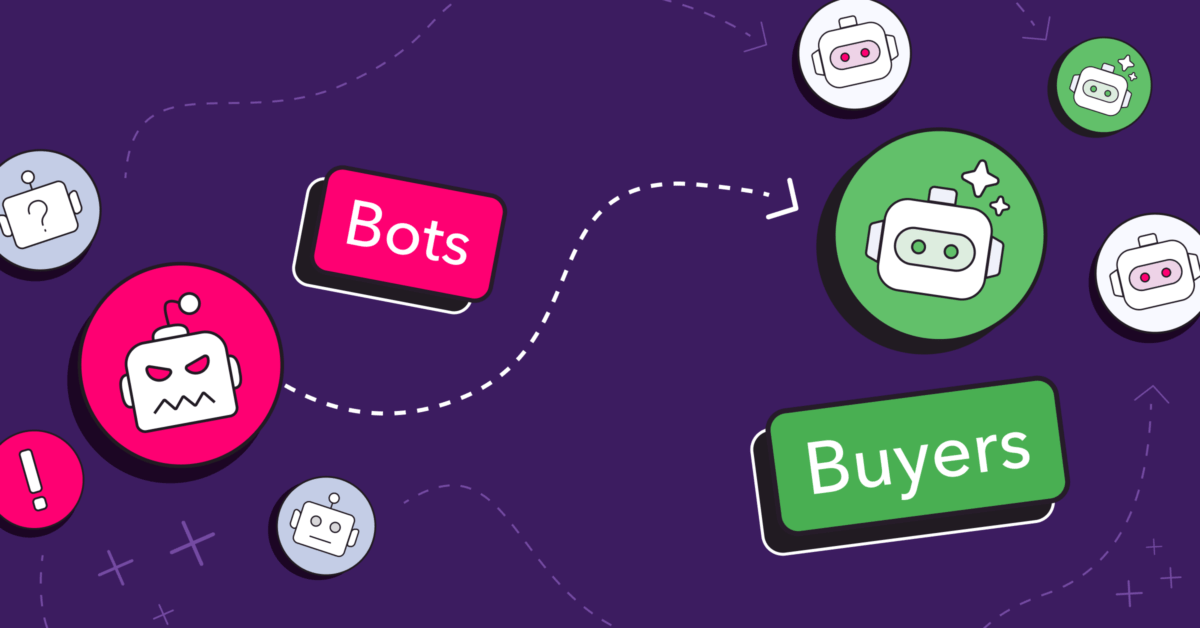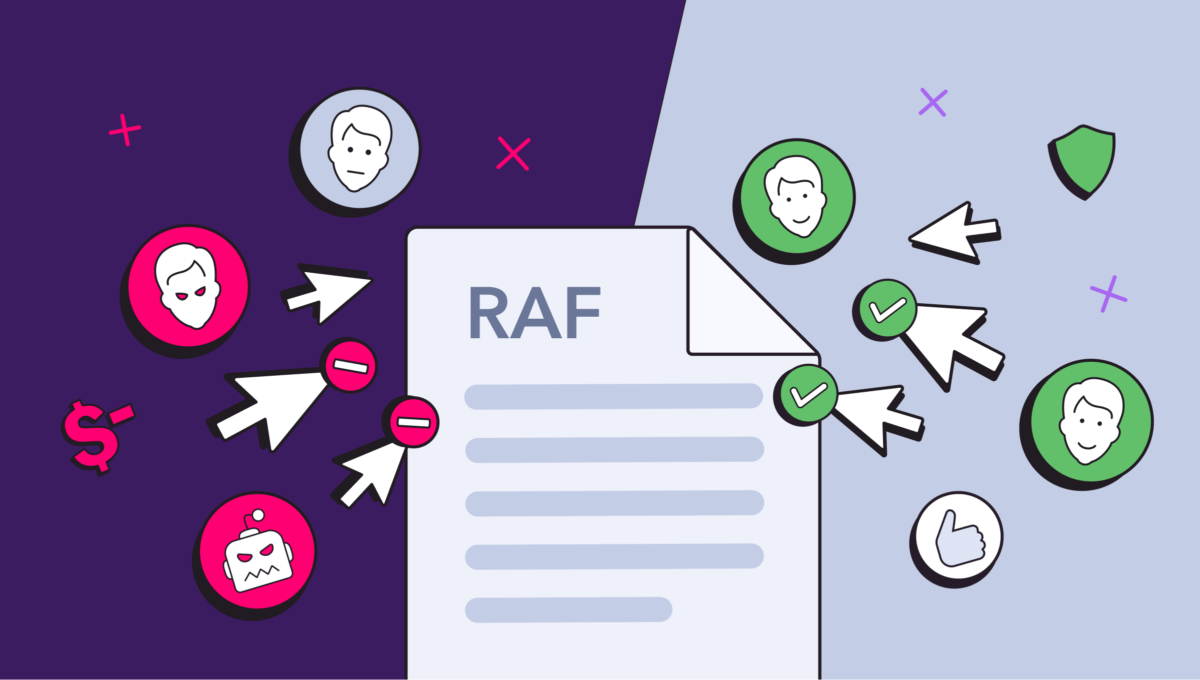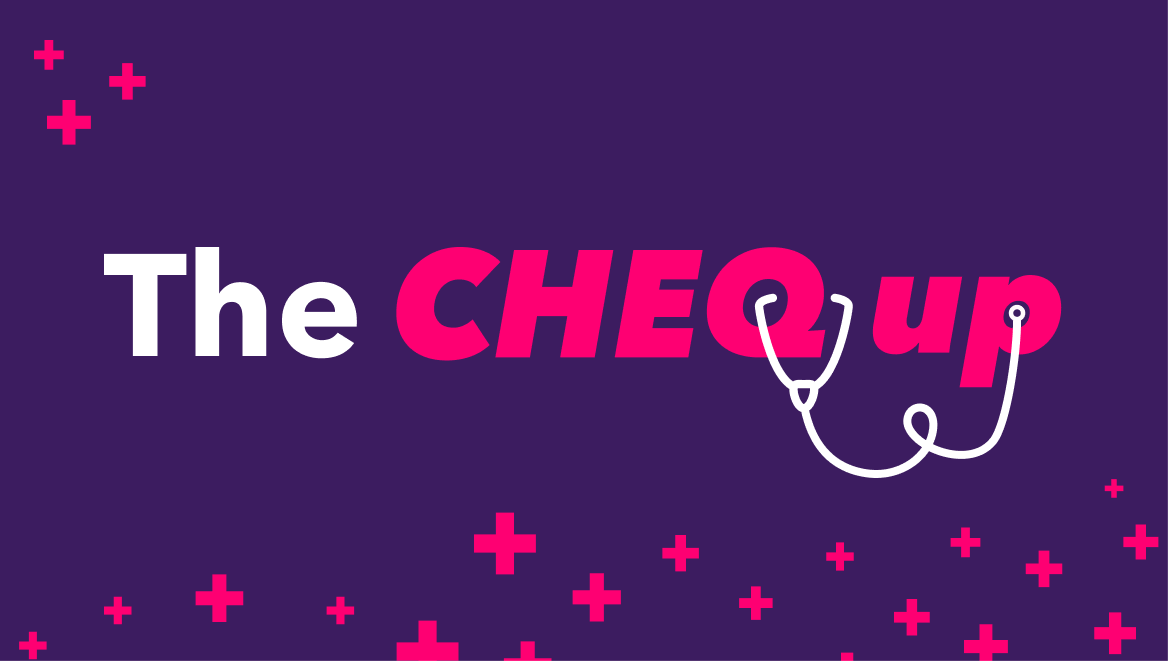ECサイトにおける不正注文のリスク 手口と対策方法を紹介!
Yukie
|Web サイト運用・セキュリティ対策 | 2025年7月01日
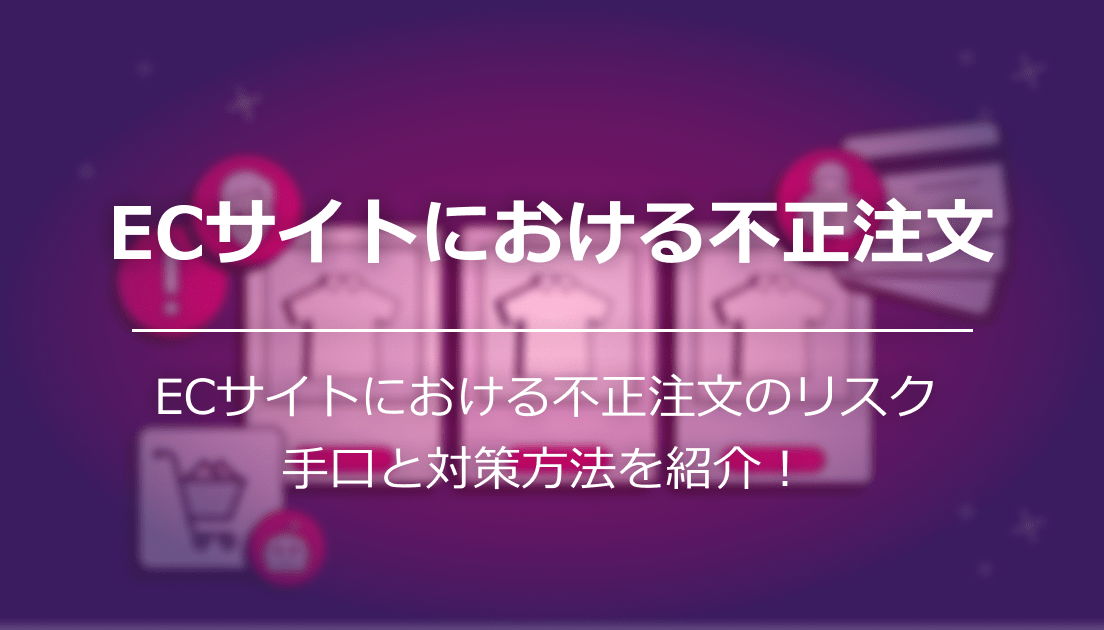
オンラインショッピングやフリマアプリの普及に伴い、ECサイトでの不正注文、とりわけクレジットカードの不正利用の被害が増加しています。経済的損失はもちろん、ブランドイメージの低下につながる可能性もあるのが不正注文の怖さです。本記事では、ECサイトでの不正注文のリスクや代表的な手口、防ぐための対策方法を紹介します。
ECサイトの不正注文が引き起こす問題
通常の注文ではなく、詐欺や転売目的での悪質な不正注文は、ECサイト運営者にさまざまな問題を引き起こします。
不正注文が引き起こす主な問題
- 広告費のムダが発生
- 通常の注文処理の遅延
- 返品、返金手続きのコスト増加
- 本来のクレジットカード保有者とのトラブル
こうした問題が発生すると、経済的損失だけでなく、ブランドイメージや顧客からの信頼低下につながる可能性があります。
ECサイトで見られる不正注文の手口
オンラインショッピングやフリマアプリの普及により、不正注文の手口は年々巧妙化しています。代表的な例に挙げられるクレジットカードの不正利用以外にも、返金詐欺や転売目的の大量注文など、さまざまな手口が使われているのが近年の不正注文の実態です。
クレジットカードの不正利用
一般社団法人日本クレジット協会の調査によると、2024年のクレジットカード不正利用の被害額は過去最多の555億円を記録しました。2020年の253億円と比べると2倍以上となっており、ここ数年で被害額が急激に増加しているのが実態です。手口としては、架空のサイトやメールから個人情報を盗み取る「フィッシング詐欺」や、特殊な端末を使った機器を使ってカードを偽造する「スキミング」が主に用いられています。
クレジットカードの不正利用は、カードの所有者である顧客自身はもちろん、ECサイト運営者も「チャージバック」の被害を受ける可能性があります。チャージバックとは、顧客から不正利用の報告を受けたクレジットカード会社が、ECサイトでの売上を取り消す対応です。3Dセキュアやチャージバック保険を利用していない限り、商品の代金はECサイト運営者が負担しなければなりません。
参照元:一般社団法人日本クレジット協会|クレジットカード不正利用5つの対策
返金詐欺
購入者が虚偽の理由(商品未着・破損・不良品など)を申告し、不正に返金を要求する詐欺行為も見られます。例えば、ブランド品のバックの購入者が、その商品が本物であるにもかかわらず偽造品だと主張し、返品しないまま購入代金だけを返してもらおうとするような行為です。
商品は購入者の手元にあるままで、購入代金だけを返す形になれば、ECサイト運営者にとっては大きな損失につながります。また、返金詐欺への対応で発生する手間や人件費など、直接的な損失以外の隠れたコストも無視できません。
転売目的の大量注文
ボットや複数のアカウントを使って人気商品を買い占め、高額で転売する手口もあります。狙われやすい商品は、個数制限のある限定品や人気アニメ・ゲームのキャラクターグッズなどです。純粋に商品を求める正規の顧客が購入できなくなり、ブランドイメージや在庫管理に悪影響を及ぼす危険性があります。
市場での正確な需要を測れなくなる社会問題でもあるため、各メーカーや小売業者はさまざまな対策を講じています。例えばゲーム業界では、人気ゲーム機の予約購入にあたり、過去のプレイ時間や利用状況を応募条件に含める企業が登場し話題になりました。
ECサイトの不正注文の対策方法
クレジットカードの不正利用や返金詐欺など、さまざまな不正注文の被害を防ぐには事前の対策が必須です。万が一、不正注文が発生した場合にも被害を最小限に抑えられるよう、以下に紹介する対策を行いましょう。ECサイトをより安全に運営するには、複数の対策を組み合わせてユーザーからの信頼を得ることが大切です。
3Dセキュアの導入
3Dセキュア(本人認証サービス)は、顧客が本人であることを追加の認証手段で確認する仕組みで、パスワードやワンタイムコード、生体認証などが用いられます。3Dセキュアにより本人認証を強化することで、チャージバック発生時にEC事業者が免責されるケースがあります。ただし、適用にはカード会社や決済プロバイダーの条件を満たす必要があるため、導入時には確認が必要です。
3Dセキュア以外のチャージバッグ対策では、保険に加入する方法があります。一定額の補償を受けられる点や、国内ECに比べてチェックが難しい越境ECの不正注文に対応できる点がメリットです。
チャージバックの被害に遭えば大きな損失につながるため、3Dセキュアの導入もしくは保険の加入による対策が欠かせません。また、ECサイト上に返金ポリシーを明記し、返金詐欺対策を講じることも大切です。
フィッシングサイトの検知
顧客が誤って情報を入力しないよう、不正なフィッシングサイトを早期に発見する対策が不可欠です。フィッシングサイトは実在のECサイトや金融機関と見間違えるほど巧妙に作られており、顧客が気づかないうちに個人情報やクレジットカード情報を入力してしまうケースがあります。
自社のフィッシングサイトが作られてしまうと、クレジットカードの不正利用、売上減少や信用低下などの問題を引き起こすため、被害を未然に防ぐことが大切です。検知ツールによる監視や、顧客からのフィードバックの収集が対策に効果的です。また、フィッシング詐欺から顧客を守る対策として、注意喚起の実施やSSLサーバー証明書の導入も検討できます。
脆弱性診断
クレジットカードの不正利用や、転売目的の大量注文のリスクを軽減するには脆弱性診断が有効です。脆弱性は、OSやソフトウェアの不具合・設計ミスによって生まれるセキュリティ上の欠陥です。ECサイトやオンラインプラットフォームの脆弱性が、不正注文やデータ盗難などの攻撃の入口になる場合があるため、早期に発見・修正する必要があります。
また、近年は「ゼロデイ攻撃」という新たなサイバー攻撃の手口が注目を集めています。OSやソフトウェアの開発ベンダーが脆弱性を発見して修正プログラムを提供する前に攻撃を仕掛けるため、極めて対策が難しいのが特徴です。ゼロデイ攻撃に対応するには、定期的なセキュリティ診断とシステムのアップデートを心がけるのはもちろん、適切なベンダー選びと検知ツールの導入も重要です。
トランザクション監視・不正検知
ECサイトやオンラインプラットフォームにおけるすべての取引(トランザクション)をリアルタイムで監視し、不正注文を検出・防止する対策も効果的です。監視が必要な取引例としては、「短時間に多数の高額商品を注文」「配送先住所が不自然」「クレジットカードの利用場所が突然海外に移った」などが挙げられます。
こうした異常な注文や決済を検出することで、不正注文を早期に発見し、返金詐欺や大量注文の被害を最小限に抑えられます。自社のノウハウや体制が十分でない場合は、大手ECサイトやカード会社が運用しているデータベースを利用するのもひとつの手段です。ユーザーの行動や不正注文の配送先情報を蓄積するには時間がかかるため、必要に応じて外部サービスの利用を検討しましょう。
顧客データプライバシーの保護
顧客データが流出すると不正注文に悪用されるリスクが高まり、企業の信頼度が下がるおそれがあります。情報漏えいや不正注文を防ぐため、ECサイトやオンラインプラットフォームの個人情報を適切に管理する対策が必要です。
プライバシー保護の対策例には、顧客データの暗号化やアクセス制限、多要素認証の導入などが挙げられます。多要素認証とは、パスワードの入力(知識情報)に加え、登録済みの携帯電話に送信されたワンタイムパスコード(所持情報)も入力するなど、複数の要素を組み合わせた認証方法を指します。
個人情報が流出すれば企業の長期的な経営に悪影響を及ぼしかねないため、データ保護のガイドラインに従ったECサイトの運用が求められます。
CHEQ で顧客の信頼を維持し EC サイトのセキュリティを確保
CHEQ は、世界初のファネル全体を保護するセキュリティプラットフォームです。ECサイトを含むWebサイト全体の疑わしいトラフィックに対して2,000件以上のセキュリティチェックを行い、悪意のあるアクティビティ検知し、リアルタイムにブロックすることで不正行為に適切に対処することを可能にします。これにより、対処療法的な詐欺対策に振り回されることなくECサイトの運営に注力していただくことが可能です。
まとめ
不正注文には、コスト増加や通常の注文処理の遅延、ブランドイメージの低下など、さまざまな問題を引き起こすリスクがあります。あらゆるECサイトが被害を受ける可能性があるため、事前にきちんとした対策を講じましょう。自社サイトが被害を受けていないか不安な方は、まずはCHEQの無料セキュリティ診断をお試しください。